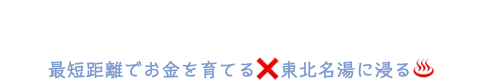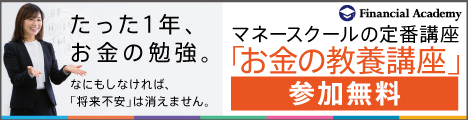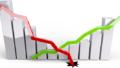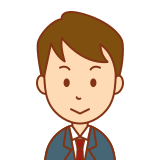
キャッシュフローって何?
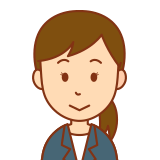
売上や利益とどう違うのかしら?
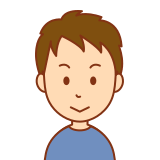
なぜキャッシュフローが重要なの?
今回は「利益とキャッシュフローの違い」について説明します。
利益とキャッシュフロー(現金収支)の違いがいまいちわからない!
これ、なかなかわかりづらいですよね。。
そこで経理歴17年の部長代理がわかりやすくお伝えします。
企業や投資家にとってキャッシュフローはめちゃくちゃ大事です!
キャッシュフローを知ることで、経理マンや企業経営者だけでなく、株式投資にも役立ちますので、ぜひ最後までお読みください。
利益とキャッシュフロー(現金収支)の違い

キャッシュフローとは、直訳すると資金の流れ、すなわち現金収支のことです。
会社の利益はどうやって計算されるかというと、一般的には「会社の売上から、かかった費用(コスト)を引いたもの」です。
これに対してキャッシュフローは「会社に入ってきたお金(収入)から、出ていったお金(支出)を引いたもの」です。
イメージは家計簿に近いかもしれません。
売上や費用は「会社の帳簿上の数字」ですが、現金収支は「実際の現金の出入りの記録」です。
一見、2つの数字はピッタリ合いそうな気もしますが、何故合わないのでしょうか。
それは認識されるタイミングが違うからです。
売上や費用は発生主義といって、現金の収支とは関係なく、取引が発生した時点で売上や費用を認識するルールとなっています。
この「現金の収支とは関係なく」というところがミソです。
売上を認識するタイミングは、サービスであれば「サービスの提供が完了した時」や、請負であれば「目的物を引き渡した時」などに計上します。(実際はもっと厳密に「実現主義」という基準で計上していますが、ここでは割愛します)
これに対して現金収支は、実際にお金が出入りしたときに認識されます。
実際に売上を計上しても、イコール現金が入ってくるとは限りません。
会社では「売上を計上したあとに請求書を発行し、お客様からの入金は翌月末」といった商慣習が一般的ではないでしょうか?
売上を計上した瞬間にお金を頂けるケースもありますが、稀なケースだと思います。
このような掛け売りでは「売上と現金の入金」はタイミングは異なります。
※現金払いしかできない駅の売店などであれば、「売上=現金入金」となりますが、クレジットや掛売りなど後払いの仕組みがあれば、タイミングはズレることになります。
費用と現金支出についても同じことが言えます。
つまり「売上・費用」と「現金収支」は認識するタイミングが異なるので、「利益(売上ー費用)」も現金収支と合わないのです。
キャッシュフローが企業経営や株式投資に重要な理由

みなさんは会社の安定性や今後の継続性を知りたいとき、何をみますか?
決算書や有価証券報告書に書いてある「売上」や「利益」をみますよね。
確かに事業がうまくいっているかをみるのに、売上や利益は重要です。
ただ、それだけでその会社が安定しているかどうか判断できますか?
そもそも、その決算書の数字は信頼できる数字ですか?
決算書の売上や利益は会社の成績表なので、その年度の業績の良し悪しはわかりますが、長期的な会社の安定性や継続性までは判断が難しいです。
さらに、決算書の売上や利益の数字はいくらでも操作をすることができます。
事実、有名企業による粉飾決算などのニュースも後を絶ちませんよね。
では何を見れば良いのでしょうか?
会社の安定性や継続性などの情報を見たい場合は、「キャッシュフロー(現金収支)」を見るようにしましょう。
なぜキャッシュフローが大事かといいますと、現金がないと企業活動が何もできないからです。
現金がないと家賃や電気代などの固定費が払えませんし、中小企業などでは、通常の企業活動をするベースとなる資金を安定的に確保することは、最優先の経営課題です。
逆に現金をたくさん保有していれば、新しい投資もできますし、社員に還元することもできます。
現金をたくさん確保できる会社は、安定して企業活動ができるのです。
このように、キャッシュフローは企業活動を安定して継続するのに大変重要な要素なのです。
まとめると、なぜキャッシュフローを見ることが大事かと言いますと、
キャッシュ(現金)は、
・企業にとっての「血液」である
・故意に操作できない「信頼性の高い数字」であり
からです。
利益が「栄養」だとすると、キャッシュは「血液」だから
企業活動にとって利益は栄養、キャッシュは血液といわれています。
いくら栄養(利益)を取っても、血液(現金)がなければ体中に栄養を送ることができません。
人間と同じで、栄養(利益)はある程度とらなくても即死はしませんが、血液(現金)がなければ即死します。
企業は利益という栄養を継続的に得ることと同時に、現金を安定的に確保してこそ「いい企業活動」につながるのです。
利益は現金を得るための「手段」に過ぎません。
【TOPIX】倒産とは「現金が払えなくなること」
現金が血液だという理由は、会社の倒産を例にあげればわかりやすいかと思います。
倒産とは「支払いの義務があるのに、それができなくなること(=債務を弁済することができなくなること)」をいいます。
簡単にいうと、取引先への支払いや、銀行へ借入金の返済ができなくなってしまうこと。
つまり、支払いの義務に応じられない=現金がないから払えない=倒産
ということです。
倒産が発生する直接の原因は「利益が赤字」だからではなく「払える現金が尽きた」からなのです。
利益が赤字であることも倒産の間接的な原因になりますが、赤字でも現金があれば支払いはできますので、しばらくは企業活動を続けられます。
しかし現金がなくなってしまえば、すぐにでも倒産してしまうのです。
逆に赤字でも現金があるかぎりは企業活動を継続することができます。(借金などをして現金を増やせれば生き延びることは可能)
例えば、コロナ禍で赤字に転落する企業が続出するも、実際に倒産する企業件数は少ないのが実情です。
これは国が緊急措置として無利子で融資をしている(お金を貸している)からで、現金を確保できているからです。
利益は操作できるが、キャッシュ(現金)は操作できない信頼性の高い数字
キャッシュフローを見るべきもう一つの理由は、キャッシュ(現金)は故意的に操作することが難しいからです。
現金収支は、企業や人の思惑によって故意に操作することが難しいので、外部から見れば信頼できる数字なのです。
ところが利益は、企業の都合によって故意に操作することが可能です。
先ほど「売上や費用は帳簿上の数字」と説明しましたが、売上や費用を計上するタイミングは、ルールに則っていればある程度企業の判断に委ねられており、裁量の余地があります。
東芝の不正会計事件で発覚したように、「工事進行基準」などは企業の裁量によって簡単に売上を操作できてしまう最たる例です。(もちろん不正な操作は許されません)
一方、現金収支は操作が難しいです。
お金が入れば現金が増え、お金を払えば現金が減る、その事実に合わせて帳簿に記載するだけなので、故意に操作する余地はほぼありません。
実際のお金の動きと帳簿の金額に不一致があればすぐにわかってしまいます。
さらに現金の帳簿残高は、金庫にある現金や銀行の預金残高証明書などと照合し、一致させることが大前提です。
帳簿と現物が1円でも合わなければ、経理担当は必死になって原因を追究しますよね?
このように、現金の出入りを操作することは難しいのです。
だからこそ、現金収支の帳簿の数字は、嘘を書きにくい信頼性が高いものといえます。
キャッシュ(現金)が潤沢な会社は社員の幸福度も高い!?
キャッシュが潤沢な会社であれば、新しい投資を思いっきりやることができます。
従業員にも給料アップとして還元することができ、従業員も幸せです。
従業員が幸せになれば、サービスの質も上がります。
このように現金がたくさんあれば、プラスのスパイラルが形成されやすいです。
逆に現金がない会社は
- 給料カットや家賃を下げるために安い狭いオフィスに移動する
- 社員のモチベーションは低下する
- 人間関係も悪化する
- サービスの質が低下してお客さんも離れ、最終的に倒産へ
といった「負のスパイラル」が形成されそうです。。
よって、キャッシュは豊富にあることに越したことはありません。
株式投資家もキャッシュフローを見るべし

キャッシュフローを重要視する考えは、会社経営に限らず株式投資でも使えます。
配当金目当てのインカムゲイン投資家であれば、配当金支払の原資となるキャッシュフローを安定して獲得できている銘柄を探しましょう。
特にキャッシュフローの中でも「フリーキャッシュフローが多い企業」が良いと思います。
配当を支払うには現金が必要です。
いくら利益が出ていても、手元に現金がなければ配当金を払うことはできません。
よって、株式投資での銘柄選びは、株価や売上の伸長などで判断するのではなく、配当金を安定的に払い続けられるために、安定したキャッシュを獲得しているかで選ぶ必要があります。
株式投資をされている方は、同じ見方で銘柄を選べば長期的に高配当を得ることができるようになります。
さらにその会社のビジネスモデルが、安定したキャッシュフローを獲得し続ける仕組みであればなおよしです。
このように、企業の利益や短期的な株価の上下動はあまり気にする必要なく「配当を支払うだけのキャッシュを継続的に獲得できるかどうか」が銘柄選びのポイントになります。
【結論】経営者は現金よりもキャッシュフローをみよ!
キャッシュフローの大切さについてお伝えしました。
経営者は「売上売上!」「利益利益!」と言いがちですが、重要な順に言えば「現金>利益>売上」です。
「現金を獲得するための手段」としての利益であり、「利益を獲得するための手段」としての売上なのです。
いかに売上を上げていても利益が伴っていなければ、タダ働きをしたことと同じですし、利益が上がっていても取引先の倒産などで現金が入らなければ、結局利益は損失に変わります。
投資も経営も現金の重要性を忘れずに、良いスパイラルを築いていきましょう!
ではまた。
経理マンのキャリアアップに役立つ情報を発信中👇
Tweets by settakick